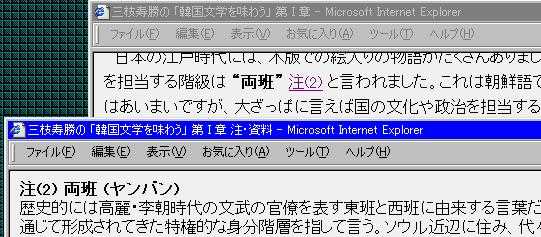
|
この記事は、国際交流基金アジアセンターが開催した アジア理解講座 Asia Center Lecture Series 1996年度 第3期 (1997年1月) 『韓国文学を味わう』 報告書として出版されたものです: |
||||||||||||||
|
| この画面以下のページの参照方法: |
| 目次 や 注 をクリックすると、新しい窓が開きます。 |
| 各窓を例えば次のように配置すると、複数の窓はそれぞれ同時に表示できます: |
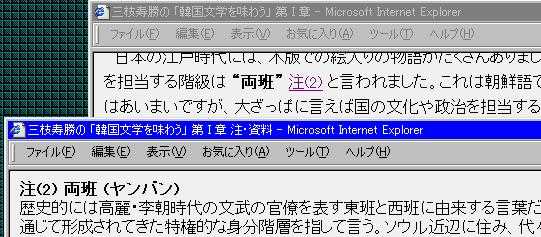 |
- 近代文学と近代史
- 前近代の文学
- 《古代小説》
- 近代文学の芽生えと表記の変遷
- 《新小説》/李人稙(イ・インジク)の「血の涙」
- 金時習の『金鰲新話』に見る伝来と受容
- 『金鰲新話』/『剪燈新話』/『伽婢子』
- 『金色夜叉』を翻案した新小説『長恨夢』
- 日本に伝来した『春香伝』と翻訳の問題点
- 古代小説を生んだパンソリ
- 『春香伝』(「春香歌」)/『沈清伝』(「沈清歌」)/『興夫伝』(「興夫歌」)/『水中歌』/『赤壁歌』
- 文学作品とパンソリのユーモアと諧謔
- 金芝河(キム・ジハ)の「五戝」/朴常隆(パク・サンニュン)の『死についてのある研究』/李文求(イ・ムング)の『うちの村』
- 波乱の生涯
- 朝鮮初の本格的長編小説「無情」
- 「民族改造論」ほか
- 近代文学における李光洙の存在意義
- 近代詩の系譜
- 朱耀翰(チュ・ヨハン)/金素月(キム・ソウォル)/韓龍雲(ハン・ヨンウン)/鄭芝溶(チョン・ジヨン)/金起林(キム・ギリム)/李箱(イ・サン)/白石(ペク・ソク)/李庸岳(イ・ヨンアク)/李陸史(イ・ユクサ)/尹東柱(ユン・ドンジュ)
- 大河小説の始まり ―― 洪命憙の『林巨正』
- 各ジャンルにおける大河小説
- 金来成(キム・ネソン)の『青春劇場』(5部作)/李箕永(イ・ギヨン)の『豆満江』(3部作)/朴景利(パク・キョンニ)の『土地』(5部作16巻)/黄皙暎(ファン・ソギョン)の『張吉山』(10冊)/金周榮(キム・ジュヨン)の『客主』(10冊)と『禾尺』(5冊)/趙廷来(チョ・ジョンネ)の『太白山脈』(10冊)/朴泰遠(パク・テウォン)の『甲午農民戦争』(3部作)/(北)《四一五作家集団》の叢書『不滅の歴史』
- 純文学の作家たち
- 自然主義の作家/モダニズムの作家/李泰俊(イ・テジュン)と《九人会》
- プロレタリア文学の誕生とその限界
- 《カップ》の結成/林和(イム・ファ)の「うちのお兄さんと火鉢」/崔曙海(チェ・ソヘ)の「紅焔」/趙明煕(チョ・ミョンヒ)の「洛東江」/李箕永(イ・ギヨン)の「故郷」/宋影(ソン・ヨン)の「交代時間」
- 暗黒時代の文学
- 《親日文学》/崔載瑞(チェ・ジェソ)の「民族の結婚」/崔秉一(チェ・ビョンイル)の『梨の木』
- 文学運動の分裂
- 文学のテーマとなった解放の意義
- 金松(キム・ソン)の「武器のない民族」/金萬善(キム・マンソン)の「ハングル講習会」/金萬善(キム・マンソン)の「二重国籍者」/金来成(キム・ネソン)の「混血児(原題:民族の責任)」
- 親日文学のその後
- 《鳳凰閣座談会》/李泰俊(イ・テジュン)の「解放前後」/蔡萬植(チェ・マンシク)の「民族の罪人」
- 解放直後の詩集と雑誌
- 深まる朝鮮戦争の傷跡とタブーの成立
- 戦争文学
- 朴鳳宇(パク・ポンウ)と林和(イム・ファ)の詩/廉想渉(ヨン・サンソプ)と韓雪野(ハン・ソリヤ)の小説
- 1950年代の文学
- 孫昌渉(ソン・チャンソプ)/李範宣(イ・ボムソン)/金声翰(キム・ソンハン)
- 1960年代の文学
- 金洙暎(キム・スヨン)/申東曄(シン・ドンヨプ)/崔仁勲(チェ・イヌン)/金承nq(キム・スンオク)/南廷賢(ナム・ジョンヒョン)
- 1970年代の文学
- 金芝河(キム・ジハ)/申庚林(シン・ギョンニム)/崔仁浩(チェ・イノ)/朴婉緒(パク・ワンソ)/李清俊(イ・チョンジュン)/連作小説
- 内面化されるさまざまな問題
- タブーを扱う小説の登場
- 時代を代表する2人の小説家
- 李文烈(イ・ムンニョル)/梁貴子(ヤン・グィジャ)
- 若者たちのベストセラー詩集
- ト・ジョンファンの『花葵のあなた』/ソ・ジョンユンの『ひとり立ち』
- 民主化宣言後の文学界
- 越北作家の全面解禁/《後日談文学》/女性作家
作品集索引
韓国文学史関連年表
日本語参考文献