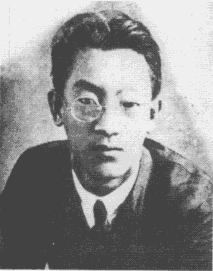 |
|
金東仁(キム・ドンイン/1900〜51) 出典:編輯委員会編『韓国作家アルバム』三省出版社、1972 |
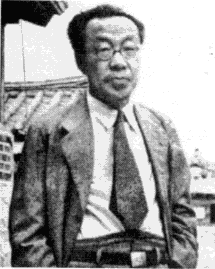 |
| 廉想渉(ヨム・サンソプ/1897〜1963) 出典:編輯委員会編『韓国作家アルバム』三省出版社、1972 |
| |||
|
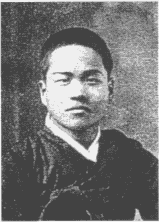 |
|
羅稲香(ナ・ドヒャン/1902〜26) 出典:『韓国小説文学大系 22』東亜出版社、1995 |
 |
|
李孝石(イ・ヒョソク/1907〜42) 出典:李孝石『李孝石全集 1』創美社、1983 |
 |
|
李泰俊(イ・テジュン/1904〜?) 出典:李泰俊『李泰俊文学全集 月夜』キップンセム、1995 |
 |
| 金裕貞(キム・ユジョン/1908〜37) 出典:金容誠『韓國現代文學史探訪』国民書館、1973 |
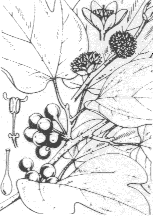 |
|
注(13) 冬柏の花 従来「椿の花」とされてきたが、本当は小さくて黄色い花を咲かせる「だんこうばいの花」のこと。赤い椿と黄色いだんこうばいとでは、イメージが全く異なる。 出典:李昌福『大韓植物図鑑』郷文社、1979 |
 |
|
蔡萬植(チェ・マンシク/1902〜50) 出典:金容誠『韓國現代文學史探訪』国民書館、1973 |
|
注(14) 九人会 当初のメンバーは、金起林、李孝石、李鐘鳴、柳致真、趙容萬、李泰俊、鄭芝容、李無影。その後、李孝石と、新聞記者だった李鐘鳴、金幽影の3人が抜けた代わりに、朴泰遠、李箱と北へ行った詩人・朴八陽(パク・パリャン/1905〜88)が加わった。最終的には、劇作家の柳致真と新聞記者の趙容萬が抜け、金裕貞と評論家の金煥泰(キム・ファンテ/1909〜44)が入った。 |
| |
| |
|
その後1927年には、プロレタリア文学はただ反抗しているだけではだめだ、政治的な意識と方向性をしっかり持たせなければいけないということで第1次方向転換をします。また1931年の第2次方向転換は、ボルシェヴィキ化・党の文学とよく言われますが、共産党主導の文学を目指したということです。第2次方向転換の時には若くて元気な人が参加しましたが、すぐあとに大々的な検挙が2回もあり、1935年に解散してしまいます。ですから、日本より少し遅れるのですが、動き出してから解散するまで長目に見ても10年でこの歴史は閉じるわけです。
中西伊之助歓迎座談会(1925年8月17日開催)時に撮影されたもので、朝鮮プロレタリア芸術同盟の準備の集まりと言われている
後列左より宋影、崔承一、金基鎮、朴英煕、李益相。前列左より金永八、李赤暁、李浩、中西伊之助、朴容大、金nq)
出典:権寧nq「中西伊之助と1920年代の韓国階級文壇」『社会文学 第7号』日本社会文学会、1993. 7. 30
| |||
|
 |
|
崔曙海(チェ・ソヘ/1901〜32) 出典:金容誠『韓國現代文學史探訪』国民書館、1973 |
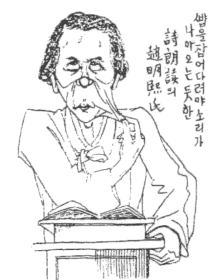 |
|
趙明煕(チョ・ミョンヒ/1894〜1942)似顔絵 安碩柱画 出典:『別乾坤』開闢社、1927 (説明文訳)頬をひっぱると声が出てくるような詩朗読の趙明煕氏 |
 |
|
宋影(ソン・ヨン/1903〜79) 出典:金允植『林和研究』文学思想社、1989 |
| ||||||||
| |||
|
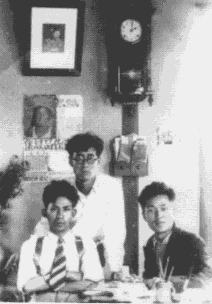 |
|
金素雲(キム・ソウン/1907〜81) (写真右より金素雲、朴泰遠、李箱)著者蔵 |
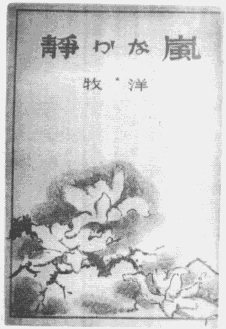 |
|
李石薫(イ・ソックン/1908〜50?)の著書表紙 牧洋(李石薫)『静かな嵐』毎日新報社、1943 |
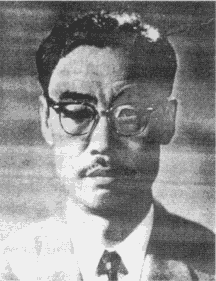 |
|
崔載瑞(チェ・ジェソ/1908〜64) 出典:韓国民族文化大事典編纂部『韓国民族文化大事典』韓国精神文化研究院、1991 |
 |
|
崔秉一(チェ・ビョンイル/生没年不明)の著書表紙 崔秉一『梨の木』成文堂書店、1944. 12 |
|
会が始まるまでなかなか集まらな[か]つた。殆んどが農家で松林と竹薮の間により固まり町名はついてゐても片田舎であつた。班長さんが待ちくたびれて、再び、集まつてない家々を廻つてやつとこさ会が始まつた。七時の予定が九時頃であつた。松林のなかの尼さん、濁酒売りの婦、よぼよぼの腰の直角にまがつたお婆さん、それに、てらてら額の禿げ上がつた老人や、防寒帽を被つた、長い房々したひげの真白い、絵本の中にでも出て来さうなサンタクローズみたいな爺さん、白い喪服に夏の褪色したパナマ帽をのせていやに四角ばつてゐる男、リンコルンみたいなあごひげとあごのそりかへつた百姓さん、昔風の頭に冠をのせた鼻の赤い書堂の先生風情の老人、それから荒くれたその日かせぎの労働者や百姓たちであつた。 みんな[皇国臣民の]誓詞が唱へられず、ここここと皇国臣民をこばかり続けた。なり、だけはわかつてゐるらしく、が、なーりと変に歌ふような調子でめいめいが尾を引いた。 「なかなか覚えられねえだが、どうすりやええだよ?」 「諺文で書いてもらつたらええだ」 このやうな人達の集まりだつたから、話は話を咲かせユーモアはユーモアを生み、無知にだまりこくつたり、悠長に時間のみ費やした。かんでくるめるやうに説明しても納得したかどうかわからない。しかし一度具体的な配給のことになると、なかなか座は活況を呈したものでめ[あ]る。 (出典:『梨の木』成文堂書店、1944) |