
出典:木村誠ほか編『朝鮮人物事典』大和書房、1995
 |
|
趙基天(チョ・ギチョン/1913〜51) 出典:木村誠ほか編『朝鮮人物事典』大和書房、1995 |
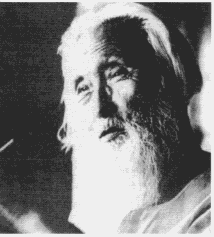 |
|
咸錫憲(ハム・ソッコン/1901〜89) 出典:咸錫憲『咸錫憲全集 1』ハンギル社、1983 |
 |
|
金松(キム・ソン/1909~88)の著書表紙 金松『武器のない民族』白民文化社、1948 |
 |
| 金萬善(キム・マンソン/1915〜?)の著書表紙 金萬善『鴨緑江』同志社、1949 |
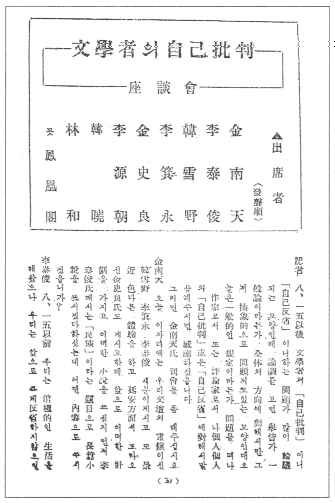 |
|
資料31 雑誌に掲載された《鳳凰閣座談会》の記録 出典:座談会「文学者の自己批判」『人民芸術 第2号』研文社、1946. 10(布袋敏博氏提供による) |
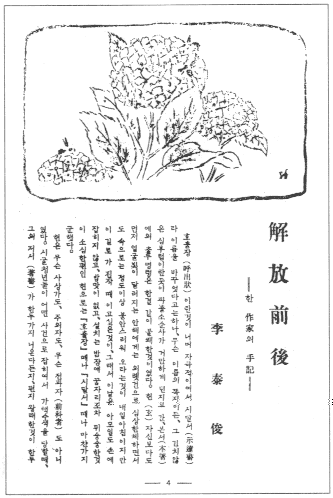 |
|
雑誌に掲載された「解放前後」第1頁 出典:李泰俊「解放前後」『文学 創刊号』朝鮮文学家同盟、1946. 7 |
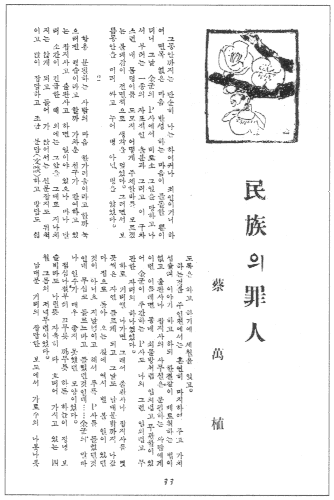 |
|
雑誌に掲載された「民族の罪人」第1頁 出典:蔡萬植「民族の罪人」『白民 第16号』白民文化社、1948. 10 |
 |
|
金台俊(キム・テジュン/1905〜49)、1936年 出典:金台俊(崔英成訳註)『譯註朝鮮漢文学史』シイン社、1997 |