
出典:姜玲珠「碧初 洪命憙 3」『歴史批評 25号』歴史批評社、1994(夏号)
 |
|
洪命憙(ホン・ミョンヒ/1888〜1968)、1930年代前半 出典:姜玲珠「碧初 洪命憙 3」『歴史批評 25号』歴史批評社、1994(夏号) |
 |
|
1958年平壌付近のある湖でボート遊びをする洪命憙(左)と金日成 出典:姜玲珠「洪命憙研究 7」『歴史批評39号』歴史批評社、1997(冬号) |
| |||
|
| |||
|
| |||
|
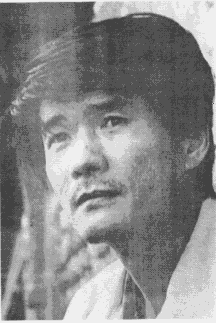 |
|
金周榮(キム・ジュヨン/1939〜 ) 出典:金周榮『夏の狩り』栄豊文化社、1976 |
注(11) 白丁(ペクチョン)
戸籍から除外された賤民で、屠殺や行李柳細工をする人々を指す。語源や起源には不明な点が多いが、白丁の語は元来一般の民の意味。高麗時代は北方民族出身の流浪民である楊水尺(ヤンスチョク)とか禾尺(ファチョク)と言われる人々がいたが、李朝時代には彼らに対する規制が厳しくなり、その結果彼らは屠殺業や行李細工、または流浪芸人となっていった。世宗時代に彼らを平民に編入して新白丁と呼んだが、その後彼らを指すのに単に白丁と呼ぶようになったと言われる。近代になって衡平社が結成され、彼らの差別に対する運動が起こされた。
 |
|
趙廷来(チョ・ジョンネ/1942〜 )、1989年 出典:『作家世界 26号』図書出版世界社、1995(秋号) |
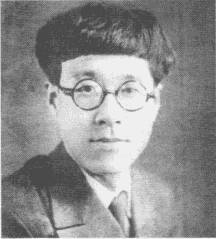 |
| 朴泰遠(パク・テウォン/1909〜86)、日本留学当時 著者蔵 |
注(12) 主体文学
主体思想、すなわち歴史的な現実に対応した革命思想に基づいた文学。具体的には金日成の抗日闘争とその過程で彼によって作られた作品を基盤にして、1970年代から1980年代にかけて提唱された文学を指す。叢書『不滅の歴史』や金日成原作の「血の海」、「花を売る娘」の再創作などがそこに属す。主体文学を提唱する過程で、植民地時代のプロレタリア文学は軽視されてきたが、1990年代になって過去の文学の伝統が再評価されるように変わってきている。
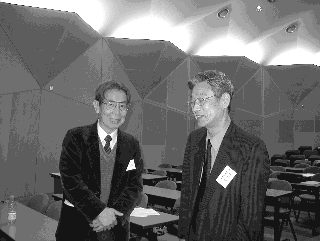 |
|
三枝壽勝(左)と金允植(キム・ユンシク、右) 2000年11月、東京大学 |