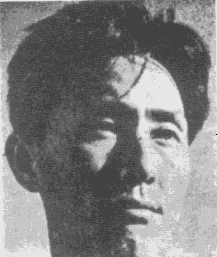
出典:白鉄ほか編『現代韓国文学全集 18』新丘文化社、1968
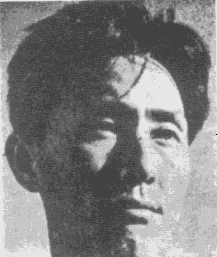 |
|
朴鳳宇(パク・ポンウ/1934〜 ) 出典:白鉄ほか編『現代韓国文学全集 18』新丘文化社、1968 |
|
||
| |||
|
 |
|
孫昌渉(ソン・チャンソプ/1922〜 )、1964年 出典:康信哉ほか編『正統韓国文学体系 (20)』語文閣、1986 |
| |||
|
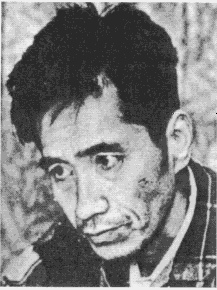 |
|
金洙暎(キム・スヨン/1921〜68) 出典:金洙暎『詩よ、唾を吐け』民音社、1975 |
青い空を制圧する / ひばりが自由だったと / うらやんだ / ある詩人の言葉は修正せねばならぬ / 自由のために / 飛翔してみたことのある / 人なら分かってるさ / ひばりが / 何を見て / 歌うのかを / どうして自由には / 血の匂いが混じっているのかを / 革命は / なぜ孤独なものなのかを / 革命は / なぜ孤独でなければならぬのかを四月革命が結局成功せずに挫折したその思いは、「青い空を」(1960)と題されたこの詩からある程度読み取れると思います。希望に燃えて明るく陽気に考えられるものではなくて、非常にうっ屈したその精神・心がここに出ています。デモを行ってそこで何かを勝ち取るというところではなく、戦いが孤独であることも既に60年代の彼の詩の中には出ています。
草が横たわる / 雨を駆ってくる東風になびき / 草は横たわり / ついに泣いた / 日が曇りさらに泣いてから / また横たわった//草が横たわる / 風よりももっと早く横たわる / 風よりももっと早く泣き / 風よりも先に起き上がるここでの「草」とは、民衆のことであると解釈されているようです。民衆は何か状況が悪くなったり天気が悪くなれば、抵抗せずにそのまま横たわっているけれども、状況が良くなればまたひと足早く起き上がるという民衆のずるさと言えばずるさであり、たくましさと言えばたくましさですが、そういう民衆の弱くてたくましい精神を歌っています。金洙暎は、少しひねくれて、うっ屈していると言えるかもしれません。この詩は民衆に結び付けているので、現在の政権の中ではかえって表に出せる詩ということで教科書にたくさん載っているのだと思いますが、詩としてそれほど優れているかどうかということは疑問です。
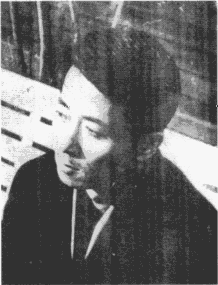 |
|
申東曄(シン・ドンヨプ/1930〜1969) 出典:申東曄『申東曄 詩選集』創作と批評社、1979 |
殻は去れ / 四月も中身だけ残って / 殻は去れ // 殻は去れ。/ 東学の年コムナル(熊津)の、その喚声だけ生きて / 殻は去れ。// そうして、ふたたび殻は去れ。/ ここでは、二つの胸とその所まで差し出した / アサダル(阿斯達)アサニョ(阿斯女)が / 中立の婚礼場の前に立って / 恥ずかしさを輝かせて / 向かい合って礼をするのだから // 殻は去れ / ハルラサン(漢拏山)からペクトゥサン(白頭山)まで / 香しい土の胸のみ残って / その、全ての金物は去れ。これは、申東曄の「殻は去れ」(1967)です。「四月」は四月革命のことで、本当は中身が残らなければいけないのに中身ではないものが残っていると言っています。そして「東学の年」は、以前話した1894年の東学農民戦争の精神ということで、80年代まで残る民族主義的な抵抗運動の象徴的な起源の芽生えがここに出ていることになります。
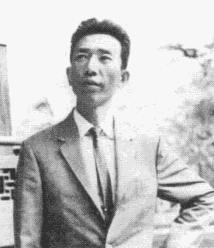 |
|
崔仁勲(チェ・イヌン/1936〜 )、1966年 出典:白鉄ほか編『現代韓国文学全集 16』新丘文化社、1968 |
| |||
|
|
出来損ないのやつらは互いに顔見るだけでも興がわく / 床屋の前に立ってマクワウリを切って / 屋台に座ってマッコルリをひっかけると / みんな等し並みに友達みたいな顔々 / 湖南(注:全羅南道のこと)の日照りの話、組合の借金の話 / 薬売りのギターの音に足踏みしてみれば / なぜこんなにしきりにソウルが恋しくなるんだ / どこかに入って花札でもやらかすか / ふところはたいて女の家でも行くか / 学校の庭に集まって焼酎にするめを裂いて / いつの間にか長い夏の日も暮れ / コムシン(注:ゴムの靴で、イメージとしては田舎者)一足またはイシモチ一匹下げて / 月が明るい馬車道をとぼとぼゆく市のあと申東曄が「鍾路五街」で田舎からソウルに出て来た労働者を描いていましたが、それを田舎のほうから見たような詩です。70年代の社会状況の一端が出ていると思います。
|
|
| |||
|
|