 韓国の小説は変わりうるか
韓国の小説は変わりうるか
 今の文学 / 何かありそうでなさそうな90年代の韓国文学
今の文学 / 何かありそうでなさそうな90年代の韓国文学
 九○年代、どこまできたか韓国文学
九○年代、どこまできたか韓国文学
 韓国の小説は変わりうるか 韓国の小説は変わりうるか
|
(三枝壽勝 1996.11) |
 今の文学 / 何かありそうでなさそうな90年代の韓国文学 今の文学 / 何かありそうでなさそうな90年代の韓国文学
|
(三枝壽勝 1998. 3.12) |
 九○年代、どこまできたか韓国文学 九○年代、どこまできたか韓国文学
|
(三枝壽勝 2000.12) |
 チョー・ソンギ 「あの島へ行きたくない」 チョー・ソンギ 「あの島へ行きたくない」 |
(山田佳子 2002.02) |
 ウン・ヒギョン 「妻の箱」 ウン・ヒギョン 「妻の箱」 |
(水野 健 2002.02) |
 キム・ジョングァン 「検問」 キム・ジョングァン 「検問」 |
(山田佳子 2001.05) |
 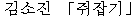 |
(岸井紀子 2001.05) |
 キム・ヨンハ(金英夏) 「非常口」 キム・ヨンハ(金英夏) 「非常口」 |
(山田佳子 2001.05) |
 ハン・チャンフン 「チュニ」 ハン・チャンフン 「チュニ」 |
(山田佳子 2001.05) |
 シンギョンスク 「浮石寺」 シンギョンスク 「浮石寺」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 ハ・ソンナン(河成蘭)の 「かびの花」 ハ・ソンナン(河成蘭)の 「かびの花」 |
(山田佳子 2001.04) |
 カンソッキョン 「茂み(森)の中の部屋」
カンソッキョン 「茂み(森)の中の部屋」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 朴媛緒パグァンソ 「(コント)私の仇のかたまり」
朴媛緒パグァンソ 「(コント)私の仇のかたまり」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 パクポムシン 「白い牛が曳く車」
パクポムシン 「白い牛が曳く車」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 新刊紹介 チョン・ソクチュ 『20世紀韓国文学の探検』全5巻(シゴンサ)
新刊紹介 チョン・ソクチュ 『20世紀韓国文学の探検』全5巻(シゴンサ) |
(三枝壽勝 2001.04) |
 パク・サンウ 「シャガールの村に降る雪」 パク・サンウ 「シャガールの村に降る雪」 |
(水野 健 2001.04) |
 ユン・ソンヒ 「33個のボタンがついたコート」 ユン・ソンヒ 「33個のボタンがついたコート」 |
(山田佳子 2001.04) |
 イ・ナムヒ(イ・ナミ) 「世の果ての路地ども」 イ・ナムヒ(イ・ナミ) 「世の果ての路地ども」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 ソン・ソクチェ 「夾竹桃の陰の下で」 ソン・ソクチェ 「夾竹桃の陰の下で」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 ソン・ソクチェ 「憑き」 ソン・ソクチェ 「憑き」 |
(三枝壽勝 2001.04) |
 チョー・ソンギ 「あの島へ行きたくない」 チョー・ソンギ 「あの島へ行きたくない」 |
(山田佳子 2002.02) |
 ウン・ヒギョン 「妻の箱」 ウン・ヒギョン 「妻の箱」 |
(水野 健 2002.02) |
 キム・ジョングァン 「検問」 キム・ジョングァン 「検問」 |
(山田佳子 2001.05) |
 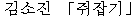 |
(岸井紀子 2001.05) |
 』の新春文芸に当選した作品である。朝鮮戦争が残した傷跡が、ねずみ取りの騒動を通じ描かれている。
』の新春文芸に当選した作品である。朝鮮戦争が残した傷跡が、ねずみ取りの騒動を通じ描かれている。 は、一年前ねずみ騒動にひとり悪戦苦闘し、ねずみ捕獲後まもなく他界した父親の人生に対して感じた、やるせなさや憤懣を思い出す。父は無力無策でありながら、意固地であった。すべてひとりで解決しようとし、たった一匹のねずみに振り回されたあげく失敗しては、雑貨屋を営む
は、一年前ねずみ騒動にひとり悪戦苦闘し、ねずみ捕獲後まもなく他界した父親の人生に対して感じた、やるせなさや憤懣を思い出す。父は無力無策でありながら、意固地であった。すべてひとりで解決しようとし、たった一匹のねずみに振り回されたあげく失敗しては、雑貨屋を営む  に、「
に、「 」と怒鳴られていた。そうした光景は、
」と怒鳴られていた。そうした光景は、 自身が学生運動で火炎瓶を投げ損ねて大火傷を負った挫折感や、幼い頃から<人民軍>というあだ名に傷つけられてきたことと深く結び付く。そのうえ、父親が死んだとき写真一枚残っておらず、遺影に使えたのは住民登録証の古びた写真のみで、そこに写し出された父親は<狭い空間に閉じ込められ、落ち窪んだ精気のない目をし、何かに怯えている>ようにしか見えない。そうした父親の人生は、
自身が学生運動で火炎瓶を投げ損ねて大火傷を負った挫折感や、幼い頃から<人民軍>というあだ名に傷つけられてきたことと深く結び付く。そのうえ、父親が死んだとき写真一枚残っておらず、遺影に使えたのは住民登録証の古びた写真のみで、そこに写し出された父親は<狭い空間に閉じ込められ、落ち窪んだ精気のない目をし、何かに怯えている>ようにしか見えない。そうした父親の人生は、 に<生>の虚無感を感じさせていた。
に<生>の虚無感を感じさせていた。 に南に来たいきさつを語る。彼は、朝鮮戦争で捕虜となり、巨済島の捕虜収容所での暴動の折、白いねずみのお陰で命拾いし、休戦協定が締結される際、南北どちらに行くかという選択を白いねずみで決定した。父親のねずみ取りに対する意固地さと、捕獲したねずみに対する残忍な処置は、自分の人生の選択への悔恨によるものだったのだろう。
に南に来たいきさつを語る。彼は、朝鮮戦争で捕虜となり、巨済島の捕虜収容所での暴動の折、白いねずみのお陰で命拾いし、休戦協定が締結される際、南北どちらに行くかという選択を白いねずみで決定した。父親のねずみ取りに対する意固地さと、捕獲したねずみに対する残忍な処置は、自分の人生の選択への悔恨によるものだったのだろう。 が子を孕んだ老ねずみを取り逃がすことをきっかけとして、父の<生>の呪縛からの解放と読み取れる。
が子を孕んだ老ねずみを取り逃がすことをきっかけとして、父の<生>の呪縛からの解放と読み取れる。 が
が  の母親なのかそうでないのか、はっきりした表現がされていないことや、
の母親なのかそうでないのか、はっきりした表現がされていないことや、 がねずみを取り逃がす直前に聞こえてきた隣家の夫婦喧嘩の声の意味など、まだまだ解釈の余地は残されている。簡潔に描かれてはいるが、含みのある作品と言えるだろう。
がねずみを取り逃がす直前に聞こえてきた隣家の夫婦喧嘩の声の意味など、まだまだ解釈の余地は残されている。簡潔に描かれてはいるが、含みのある作品と言えるだろう。 キム・ヨンハ(金英夏) 「非常口」 キム・ヨンハ(金英夏) 「非常口」 |
(山田佳子 2001.05) |
 ハン・チャンフン 「チュニ」 ハン・チャンフン 「チュニ」 |
(山田佳子 2001.05) |
『李箱文学賞受賞作品集25』文学思想社.2001.2.5.pp.25〜72.全48ページ。
| 新刊紹介 |
| チョン・ソクチュ『20世紀韓国文学の探検』全5巻(シゴンサ)2001 (三枝壽勝 2001.04) |
| パク・サンウ 「シャガールの村に降る雪」 (水野 健 2001.04) |
| ユン・ソンヒ 「33個のボタンがついたコート」 | (山田佳子 2001.04) |
| イ・ナムヒ(イ・ナミ) 「世の果ての路地ども」 | (三枝壽勝 2001.04) |
| ソン・ソクチェ 「夾竹桃の陰の下で」 | (三枝壽勝 2001.04) |
| ソン・ソクチェ 「憑き」 | (三枝壽勝 2001.04) |