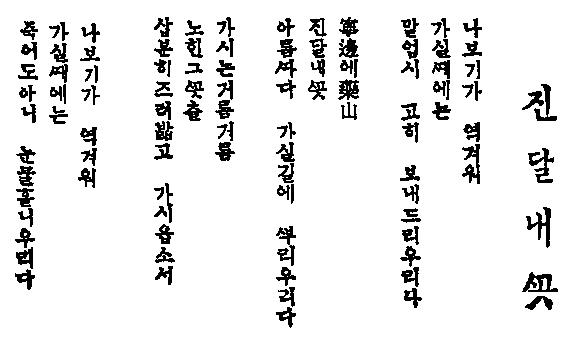ハングル工房 綾瀬 - 僕の朝鮮文学ノート 9811
Hangeul-Lab Ayase, Tokyo
ハングル工房 綾瀬店 ホームへ
文学ノート全体目次へ
Mail to home master: Ken Mizuno
981105-1: 林巨正または イム・コクチョン im-kkeok-jeong(981109-1: 追記)
「林巨正」と書いて「イム・コクチョン im-kkeok-jeong」と読む。
李朝期の大盗賊、義賊、日本の石川五衛門(?)的貧しきを助け 強きすなわち庶民の敵を打つ、伝説の英雄像。
名前の読み方の理由は、わからない。白丁 paek-jeongの子であるので、おそらく、呼び名は「幼名」を引継ぎ、何かしら純朝鮮語の意味を帯び、その名が官僚の公式記録に載ったときこの漢字が与えられたのではなかろうか。人物は実在したらしい。
その一方で、「コクチョン kkeok-jeong」は「クンシム、コクチョン」の先頭がテンソリになっただけである; 洪命憙 hong-myeong-heuiの作品ではコクチョンは忠臣の親戚でもあって、さらに「イム」を im/nim と解するなら、「主君を心配する義賊」と読めないこともないし、nim の解釈をさらに拡大するなら、愛人・家族・民族・民衆のことを心配する・文字通り義賊の名前と解することも、できるのかもしれない。
作品?の成立年代は古くない。どうさかのぼっても、『春香伝』以上にはさかのぼれないだろう。つまり、近代をむかえる時期の・李朝後期のある時代 − 日本の元禄のころのように、「義賊」伝説が生み出された。
近代以前のそれを、僕は多くを語ることはできない。ただ、朝鮮近代文学の中で 洪命憙の新聞連載小説『林巨正』を削るわけにはいかないだろう。
洪命憙は、解放前に「近代」的 文学作品を書いていた形跡はあまりない。文学作品としては ただ新聞連載の『林巨正』だけが知られていて、そしてそれが伝説的な民族文学の一部をなしていた。
ご存じの方はご存じのように、この人は解放後「北」に移動した。そして困ったことに、北の第1人者である金日成の、政治的地位でナンバー2の位置にまで登りつめてしまった。50/60年代の北の内部粛正の嵐を生き抜いたというより、おそらく高齢によって現役を退いて、その死亡も南側で確認されていた − ような気がしていたが、韓国で解禁出版された本のソデ書きには、不明になっている。1888年生まれ。
南では、解放前・つまり日本の植民地期の「民族」英雄伝 林巨正、その作者 洪命憙、という伝説が、少なくとも 1970年代には生きていた。それは、少数の専門家たちの世界を越えて、既にマンガ本の「大作」にまでなっていた。しかし「原作」である洪命憙の活字作品、その単行本は、公には出せないので、30年近い昔つまり解放前の茶色い活字本が、ごくまれに古本屋で、ひそかに、とんでもない値段で出ることはあった。
作品とその作家の名前はタブーだった − ただ、その作家が「北」に行ったということ、そして金日成の左腕にまでなったということ、ただそれだけの理由で、この作家の作品は、韓国の公式の文学史からは抹消されていた。
それから 20年。現代の写植印刷で、この作品は韓国で公刊されている。250ページ X 全10冊。
現代の感覚というか、僕の感覚で言えば、これは近代通俗型・娯楽型・講談型の、NHKの「大河ドラマ」みたいな作品だ(事実『林巨正』にも「大河歴史小説」という肩書きがついているし、同様に解禁された「越北」作家 朴泰遠 pak-thae-wonの『甲午農民戦争』にも、同じ肩書きがついていた)。生硬な民族論を説教するより、素朴な講談まわしで、あくまで娯楽として展開されるパターンの時代劇だ。
NHKの「大河ドラマ」型の絶叫はないが、話題のきまじめさにおいてNHK型ではある。ただし新聞連載らしく、その回その回で読者を次回に連れて行くうまさもある。庶民の日常を描く面は強いし、素朴でほほえましい恋もあれば、忠清道から白頭山、金剛山へと行脚する場面、その過程で怪力を発揮するコクチョンの幼い時代 ... さてさて次の巻は、と、忙しくなければ・構成も古色蒼然たる時代まわしで、楽しめる。
おそらく、「庶民の求める」作品とは、こういうものなのだ。1990年代になっても、『林巨正』はあいかわらずマンガの大作が出つづけている。こういうマンガは、TVのハデな文化とは無縁のところで、冴えない普通のおじさんやおばさんが読んでいる。
この 10年の間に、「北」に渡った作家の作品群は、南でかなり解禁されている。中には、北ではもう手に入らない、60年代の『朝鮮文学史』がソウルの書店にあったりして、奇妙な感じにとらわれることがある。そういう「復活・解禁」の流れの中で、『林巨正』は早い時期、1991年の日付がついている。
981109-1 追記:
作者の名前「洪命憙」は、僕は長い間「洪命喜」と変換して辞書登録をしていた。パソ通時代の Nifty上では、誰もこの誤りを指摘してくれなかったのだが、ホームページに乗せてから九州産大の白川豊氏から指摘をいただき、上記では修正した。白川氏に感謝します。
また氏の指摘によれば、洪命憙の没年は 1968年。これは、僕自身の記憶とも一致する。
韓国で復活・活字化されるとき、作者が洪命憙であることさえ(出版社は)隠そうとした − というウワサがある − ことに示されるように、おそらく、作者に関する情報は詳細に知られてはならないものだったのではなかろうか; だから、本のソデの解説にも、作者が「北のナンバー2になった」とは、書いてない。
981112-1: 金素月 kim-so-wolの『つつじの花 jin-dal-lae-kkoch』
画像の出典:東京外大 朝鮮語学科研究室編 『朝鮮語文体範例読本』1992
(東京外大 文学研究室 了解ずみ)
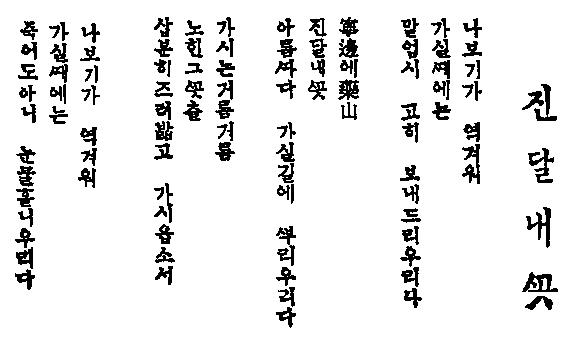
古文字が出るので「語学」に上げようかと思ったが、やはり「文学史」論に傾くので文学ということにする。
この画像は、1925+α年の、この詩集の第2版のコピーです。
画像が汚いのは了承されたい。数回コピーを経ている汚れは削ったが、あまり削りすぎると原形を失うので、可及的最低限にとどめた。
これを見て、「現代」ハングルしか見たことのない方は、驚くかもしれない。読めない文字がある; もし読者の想像力さえ豊かなら、読めない文字は「テンソリ」だと気がつくと思う。
*sk は現代綴りでは *kkであり、*st は 現代綴りでは *tt に、*sp は *pp になる。この他、現代綴りのパッチムが次の初声に書かれている; 声を出して読んでみれば、これは必ず読めるので、やってみてほしい。この第2版は、現代の出版物と完全に同じ文面になっている(つまり初版は、ちょっと文面がちがう)。
さて、ここで話題は多い。
第1に、「寧辺」に「薬山」は、現代の北朝鮮で核処理施設問題の現地である。
第2に、文字数を数えてみてもらいたい; 「金素月の七五調」問題がある。
第3に、この時代にまだ「古文字」活字が生きていること。
第4に、そういう時代に「すでに」こうした「少女趣味」の詩が書かれたこと。
第5に、別件だが作者の教師であった金億 kim-eokが、朝鮮エスペラント運動の先駆的な存在であったこと; それから、金億の時代のエスペラント運動はプロレタリア文学運動とも密接な関係があり、金億もそれにかかわっていることと、金億の職場つまり彼が「教師」であった事情、その教え子が金素月であること、そしてその金素月の詩がこんな少女趣味を示すこと、それから「日本の影響」といわれる「七五調」問題と ...
話題は、錯綜してくる。
とりあえず、書くほうも深夜になっているので、この記事は以下に続く。
981114-1: 金素月の「七五調」問題と「比較文学」
学者の世界も、一面「人気商売」である。だから、「学問」にも「はやりすたり」がある。僕が学生だった 1970年代は、各国語の個別の文学(フランスその他の西洋圏、日本では国文科の世界)は、少なくとも表面的には「研究しつくされた」時代を迎えていて、その新しい局面を開くものとして「比較文学」が注目されていた。
言語の世界で言う「比較言語学」をご存じの方は類推していただけるが、「比較言語学」は言葉を「歴史的に」比較して、その系統論をする学問だった。一方、「ある」時代のある言語とある言語を、時代に関係なく類似点や相違点を掲げるものを「対照」言語学と言う。
「比較文学」は、ある地域の文学とある地域の文学の、由来・影響・伝播とそれに伴う変形を扱うものだった。いわく、西洋の原詩が日本では七五調に訳され、その訳は既に「国文学」の財産化していること、同時に鴎外や漱石の西洋留学が、その文学に与えた「影響」といったものが、比較文学の焦点だった。
鴎外や漱石の作品が、留学先での体験を「正しく」反映していたとは限らない。むしろ作家はその体験を自分の内部に取り込んで、自分の中で消化したうえで自分の作品を生成させる。その結果、彼らの留学体験やそこから出てくる翻訳は、原文をある意味で「裏切る」面が、ある。そしてその「裏切った」結果として、今では「財産化」された明治期の「七五調」の一連の訳詩集がある。比較文学の立場は、これを「創造的裏切り」と呼ぶ。「創造的」裏切りのできない作家こそ、「模倣」するだけの2流作家だということになる。
日本では、これは流行した。外国語がきらいで国文科に入った学生たちが、これからの国文科では外国語ができなければだめだと言われて当惑する、そういう時代だった。日本では、比較文学の視点がなければ学者になる資格がない・とさえ感じられる雰囲気だった。
しかし、意外なことに、これは、朝鮮では反発が強かった。
まず、「北」が反発した。当時の「北」には文学論をする余裕があり、ときおり西側世界の文学や文学研究に言及する論文が出た。原典を見ていないが、北は、公式に「比較文学」の「影響」論に反発し、これは朝鮮民族独自の民族文学を西洋ないし日本の模倣であるとする(またはそれに隷属させる)売国奴ないし帝国主義侵略者の理論であると言っていた、らしい(「らしい」で、すみません)。
この論調は、やはり当時の在日メディアにも反映した。圧倒的な「北は天国、南は地獄」論を背景として、僕の知っている限り、当時の在日メディアが「比較文学」を擁護するものはなかった。多くは、北とまったく同じことを言っていた。それは総連傘下のメディアだけではなくて、いわゆる韓国系の出版物でもそうだった。
南ではどうかというと、事情は同じ。
70年代、文学は天下国家社会正義の木鐸たれと考える伝統的士大夫文学論は圧倒的だったし、学者・研究者の書いたものの中にも、「比較文学」に言及があるとしたら「西洋・日本の影響」論に反発するものが多かった; それを擁護するものを、僕は見たことがない。「比較文学」論の中の「影響」論は、「つまり韓国の作品は西洋や日本の模倣なのか。わが民族文学の冒涜は許せない」という反発を招くだけだった。研究者の世界も商売であって、あえて反発の予想される論文を書く必要はない。
「比較文学会」という学会は存在したが、「民族の魂」みたいな存在たちに「日本の影響あり」などと言える雰囲気ではなかった。せいぜい、作家誰それにおける西洋詩何それの受容過程、みたいな、散発的な発表があるだけだった。「影響」でなく「受容」なら、韓国でも受け入れられた。
本題の 金素月。
1970年代の文学史(の本)は、少数の新進研究者のものを除けば、古色蒼然としたものだった
記憶にあるものとしては、当事 既に「重鎮」だった 白鉄 paek-cheolの文学史(正確な書名を忘れた; ご容赦)には、「伝統的な七五調」と明記!してあったのを、今も記憶している。
「伝統的な」七五調?
「伝統的」だというなら、歴史の過去の作品たちのどこかに、七五調が存在するのでしょう? しかし事実は、李朝期にも、その前の高麗にも、百済にも新羅にも三韓にも、そういう「伝統」は見られない。歴史の中に見られないにもかかわらず、1920年代になってはじめて、突如として「伝統的な七五調」が現れるという、文学「史」として致命的な矛盾を語る本だった。
重要なことは、金素月の作品が、1920年代という時代の先端の中で、読者に新鮮な印象をもって受け入れられたこと、だからこそ この作品が歴史に残ったことだ。その「新鮮な衝撃」の理由がどこにあったのか。その多くは、漢文文体とはまた異なる節制した、禁欲的な七五調にある。それは、学生だった僕にも明らかだった。
結論を急ごう。
1973年 初版の 金允植(kim-yun-sik)/kim-hyeon共著 『韓国文学史』は、こう言う:
ju-yo-han(漢字はこちら)の後に韓国詩がその課題として負うことになった2つの問題、すなわち植民地の現実を直視しつつ、韓国人に新たなビジョンを提示することのできる新しい詩形式を発見するという困難な問題に立ち向かったのは金素月、韓竜雲、そして李相和(尚和)である。この3詩人に共通するものは、新しい詩形の探求である。時調 sijo と 唱 chang に閉じ込められていた韓国語を解放し、新しい世界を示すことのできる新形式を探求することは、植民地初期の詩人たちに与えられた唯一の任務であり、この任務を3詩人は忠実に履行する。この新しい詩形態への欲求は、おおよそ2つの類型にまとめられる。その1つは、再び時調に匹敵する新しい定型詩を発見しようとする欲求であり、それは日本の七五調に相当な影響を受けた民謡風の詩(複数)に、その先鋭な表現を得る。(...)
(原文 pp.143-144, min-eum-sa, 1995.8, 第28版、訳と強調は水野、原注を省略)
つまり、日本の「影響」を認め、それを前提として議論を進めてしまうのだ。
この文学史で、僕の疑問は解決した。
(ちなみに、金允植は当時ソウル大国文科の、kim-hyeonはフランス文学科の、それぞれ新進研究者だった。しばしば美文麗文詠嘆口調に流れる「重鎮」たちの「文学史」や、「伝統的な七五調」といった支離滅裂な説明に疑問を抱いていた僕は、この文学史の対照的な近代・翻訳調の文面に苦しみながら、さらにもう1世代新しい「朝鮮文学史」の構想なんかしたものだ)
この「文学史」以外に、僕はまだ「日本の七五調」と言い切る本を、20年以上の間 見たことがない。
おそらく、素月の「七五調」が「日本の」それであることは、韓国の研究者の間でも常識になっている。だから「常識」をあえて論文や著作に書く必要はないし、書いて反発されてもたまらない。
あえて「比較文学」の立場を言うなら、素月の七五調は「日本の」それとは大きく異なる; 一面「7・5」の形式にこだわるあまり、相当な無理がある。一面、「7・5」が前後反転することもしばしばだ。
これらを総合的に解釈するなら、素月の「七五調」は、かなりレベルの高い「創造的裏切り」を示していると僕は思う。つまり、日本の明治期の七五調は「翻訳」に発揮されたが、素月のそれは 1920年代の「創造的な」自作の詩にこそ生かされた。「源泉」を「裏切る」ことによって成り立つ文学として、素月は、ある意味において鴎外などより「模範的」でさえある。この表現は、決して皮肉ではない; 素月は、文体の開発という重大な課題に取り組んだ。鴎外は、既存の文体に依存した。素月は何もないところから、「日本」の遠い影響にヒントを得て新しいものを創造したのに対して、鴎外は気楽に「現代標準語」でものを書いただけだ。そして素月は、未知の、みずから開発した文体環境の中で、はるか遠くを見つめながら夭逝した。
1920年代、衝撃的であり(現代の感覚でいえば)少女趣味の素月の一連の詩が、新鮮なものとして歓迎された事情は、理解しよう。いや、理解すべきだ。素月の衝撃、それは 1920年代の朝鮮には、あまりにも大きな衝撃だった。
そしてそれが「日本の」七五調の「影響」下にあることは、朝鮮文学の恥部ではない。1920年代の青年にとって、それが大きな発見であり、それを自分自身のリズムに取り込んで行く過程こそが、彼の文学的成果ではなかったか。
もし それが「日本の影響」下にあるから文学的価値がないというなら、植民地下における「ほとんどすべての」文学的努力は価値がない。それは北であれ南であれ、その論理でいくなら、朝鮮人はみずから「ほとんどすべての」文学的価値を否定することになるだけだ。
981114-2: 「寧辺、薬山」と核施設
僕は、あのとき「愕然と」したものだ。
まさかと思った。
「寧辺、薬山」という地名が、現代の日本の新聞に出た。少女趣味の金素月、その代表作に出てくる地名; 短い詩なので、この4文字だけで詩全体の活字数の数%を占める、重大な地名だ。そこには、少女が禁欲的に、誰かのために散花しなければならないのだが ...
世界と歴史の残酷さ、なのだろうか。「寧辺、薬山、つつじの花」。僕は、この連鎖を「遠い未来の」こととして、空想の世界に追いやっていた。例えば、南から金剛山への観光事業がいずれ稼動し、その延長上に「朝鮮文学趣味の北朝鮮ツアー」とか、そういう時になってはじめてこの地名を新聞で見るものだとばかり、思っていたのだった。
裏返してみよう。
仮に、もしも「その」地を施設の場所としてわざわざ選択した意図が「北」にあるとしたら、これは面白いことになる。つまり、誰かさんの文学趣味; もしそうなら、これは 70年代初期まで見られた北の社会主義文学論とあまり一致しないのだが、ま、それはおいても、おもしろいなー
いずれにしても、日本でも西洋でも、核施設は「人里離れた」ところ、日本でそれが不可能な場合にも、大都市を離れた「田舎」に作られる。施主がいくら「安全だ、安全だ」と言っても、それほど安全なら東京のど真ん中につくればいいのに、必ず田舎に作られる。
つまり、「寧辺、薬山」は、今でも開発されていない田舎であることが確認されてしまったわけだ。
まあ、それだけなんですけど。
バカついでに、うちの子は女の子で、3才。入園後に4才を迎えるクラスの幼稚園に通っているのだが、このクラスの名前を「つつじ」組という。この子の誕生日が3月1日だと言えば、読者は笑ってくださるだろうか。
981118-1: 北朝鮮のある長編小説 − 笑ってもいいけどしかし「西洋」の影響
正直なところ、僕が北の小説を読んだのは 1970年代に限られる。一面では「北は天国、南は地獄」論の盛んな時代だったし、その北の「新作」小説の状況は、「学者」になるつもりだった 20代の青年としては、一応 無関心ではいられなかったのだ。
当時も、北から一連の「芸術公演」団は来た。今では伝説的な作品名になった『花を売る乙女 kkoch-pha-neun cheo-nyeo』や『血の海 phi-ba-da』は集団創作で、これには公演のシナリオも「小説」化されたものも手に入った。
が、今 話題にしたいのは、そうしたはなばなしい「集団創作」とは別のところで、昔ながらの個人創作で作者名が明記された作品のことだ。その中の1つに、もう題名も作者名も忘れた、しかし強い記憶に残っている作品がある。
長編小説つまり単行本1冊だった。事情で失ってしまったので、詳細はわからない。
作品の時代設定は朝鮮戦争、つまり「祖国解放戦争」期、1950年6月25日以後、北の人民軍は南のソウルをはるかに越えて、プサンの手前 洛東江 nak-tong-gangにまで進んでいた; 李承晩政権はプサンに避難して、玄界灘を越えて日本に脱出するかと言われたころ。従って時期は、マッカーサーの仁川上陸の直前になる; その点、この小説の設定時期に多少矛盾が発生するのだが、それは、今は目をつむることにしよう。
洛東江の攻防戦で負傷した兵士が、その野戦病院で治療を受けている。献身的に看護にあたる看護兵。しかし兵士は弱気になる。
川辺の野戦病院の窓の外には、1本の柿の木が見えている。時は秋(ここが、時期的にやや疑問が残る)。兵士は考える:
ああ、あの柿の実が全部 落ちたとき、俺も死ぬんだ
笑ったでしょ; 笑ってもいいけど、笑わなかったことにしてくださいな。
当然ながら、彼の治療に献身する看護婦は、夜の間に柿の実を「針金で」結び付けておく。二人は、北への敗走の過程で生き別れになる。
「戦後」つまり 1953年+αのピョンヤン。
ある夜。
ピョンヤン 大同江 tae-dong-gang の堤防工事の現場。工事中の堤防は、土嚢が積み上げてあるだけだ。そのほとりを、深夜 青年は何かの理由で(酒を飲んでいたのだろうか、その点は記憶がない)歩く。
青年は、ふと堤防工事の現場の、水漏れに気付く; このまま放置すれば、水漏れは土嚢の穴を破って、朝までに堤防は崩壊するにちがいない ...
青年の行動は自動的である。片腕でその穴をふさぐ; 同行した友人がいたのだったかどうか、それも作品の記述の記憶はない。
しかし、読者の期待する通り、やはり何かの事情でそこを通りかかった女性がいた; もちろん、それは あの洛東江のほとりの野戦病院の看護婦でなければならない。
こうして、二人は感動的な再会をはたす。
-----------------------------------------------------------------------
そのころ、「北」を訪問して映画を1本 持ち帰ってきた作家 小田実が、講演でこう言っていた:「北朝鮮のラブ・シーンはみんな同じだ。恋人同士が橋の上で、月をみながら革命への決意を語り合う。それが北朝鮮のラブ・シーンだ」。
僕の読んだその小説も、正確にその通りだった。あまりにも「典型的」な作品だった。そして、社会主義革命の典型的人物像を描けという当時の北の文学テーゼも、それに「正確に」一致していた。
読者の期待を決して裏切ることなく、ある深刻な状況を作り出しその状況の中で読者の期待する解決を適切に示す小説技法(を含む技法)を、「通俗小説」または「大衆小説」と呼ぶ。
僕が読んだその作品は、この技法に忠実であり、それが社会主義革命への決意を語り合う革命的恋愛の姿をとっていることで、作品の社会主義的正統性を完璧に示していると思われた。
学生だった僕は、頼まれもしないのにこの作品をレポートにして、友人・先輩・師に読ませてまわったものだ;「よくそんなもん読んだなあ」という反応が返ってきたけれど。
しかし、僕に言わせてもらいたい。
技法としての「通俗小説」の技術、「大衆小説」として社会一般に流通させることを目的としてフィクションを書き上げること; それは、当時の(まだ文学雑誌を出す余裕のあった)「北」の社会の中で、必須条件ではなかったか。当時の北の文学雑誌には、なんとも稚拙な「広告」があり、そのキャッチ・フレーズとして「小説を読もう! so-seor-eul ilk-ja!」というのがあった。「広告」という資本主義社会のそれがあることにも驚いたけど、その言い方には「小説は天下国家社会の正義を(娯楽的に)読者に体得させる回路」だということ、「小説を読むと "ためになる"」という考え方が、背後に存在したこと・だけは まちがいがない。
まとめましょうか。
70年代の北の小説に『最後の一葉』とオランダの堤防美談が出てくることは、当時の「北」の作家がそれを「知っていた」ことを証明している。逆に、大衆小説にそういうナマの話が出て来るということは、その「源泉」が読者一般に知られているわけではないことを示唆している。つまり、当時の北には、西洋文学一般が大衆に与えられていなかったであろうと考えられる; と同時に、しかし作家はそれを記憶にとどめているので、これは作家に与えられた情報的な特権か、あるいは解放前の日本を通じた情報回路の記憶によるか、いずれかだろう; 特に、2つの「源泉」は「日本で」だけ突出して知られている傾向があることを考えると、これはその経路を無視できないだろう。
当時の北の文学路線は、社会主義典型英雄論であり、かつ大衆教化を目的とするものだった。従ってそれには大衆小説ないし通俗小説の技法が必須でもあった。僕の読んだ小説は、典型的にそれを示すものだった。
余談として、「大衆小説ないし通俗小説の技法」の典型例として、日本の作家には松本清張がある。彼の作品は「しばしば」ではなく、深刻なプロット展開の後に「必ず」、それも読者の期待する以上の「偶然によって」問題が解決またはさらに展開されて行く。林和 im-hwaを主人公とする『北の詩人』をご存知の方はご存じの通り。
当時の北の作家が松本清張を読んでいたという証拠は何もない。しかし、清張型の大衆小説の技法と、社会主義(結果として)大衆小説技法の確立をめざしていた北の方向とは、奇妙によく似ている。ただしお断りしておけば、それは松本清張氏 個人とは何の関係もないことだけれど。
981129-1: 川村湊:『満州崩壊−「大東亜文学」と作家たち』/林和別伝
朝鮮文学そのものではないが、朝鮮文学を扱った評論集。株式会社 文芸春秋 1997.8 刊、¥2381。
評論集の扱う時期とテーマは、書名の表題を扱うものが3章と、これに続く数章で全9章。
今ここで話題にしたいのは、その第V章「林和別伝」と、次に第VI章「小林勝外伝」。
「林和別伝」は、松本清張『北の詩人』評だ。その意味で、特別なものではない。ただ、現在の 40代が かつて この作品を初めて読んだとき、ある種の感動とともに感じた一抹の不安を、90年代になってから活字にしてくれた意味があると思った。
清張のこの作品は、朝鮮戦争の終結期にあたる 1953年8月、北から公開された裁判記録をもとに書かれたものだ。作品を読めば明らかだが、この作品の筋立ては全面的にこの裁判記録によって成り立っているし、それは作品末尾に収録された「記録」そのものに一致する。つまり作者は、俺がフィクションを組み立てたのではない、話はこの記録にあるだけなのだと、言っている。
現在の 40代、つまり 1970年代に20才プラス・マイナス数年の年令だった読者は、この作品にある種の衝撃と不安を感じたはずだ。時代は「北は天国、南は地獄」。「朝鮮」に関心を持った当時の20才前後にとって、この圧力に抗することは難しかった。清張のこの小説は、作家一流の大衆小説の技法を動員して、「アメリカのスパイ、詩人 林和」の姿を描いていた。その意味でこの作品は、当時の総連、日朝協会、日本共産党ないし民青同盟から推薦が出ても不思議ではなかった(当時、総連と日本共産党は距離をおいた友好関係、双方の別組織として日朝協会があり、学生組織側では民青同盟がこれに力を入れていた)。
正確に言えば、僕自身がその不安を感じていた; 松本清張という有名な作家が、こういう作品を書いている。小説技法としては、手慣れたパターン。主人公の内面の葛藤、不安、その中から主人公はどのような行動を展開するかという、近代小説の手法そのものは、まず完全に成立していた。しかし、「偶然」によって場面が展開するばかりのこの作家の作品技法と、同じ原理で被告の「スパイ」罪状を立証している(はずの)裁判記録とは、あまりにも一致しすぎている。
俗な言い方をすれば、「これは話 半分で聞かなければならない」面を、僕自身が感じていたし、その世代の読者はおそらく誰もがその印象を持ったはずだと、僕は考えていた。作家の技法があざやかであり、「スパイ」林和の心理をビビドに表現して一面感動的であるからこそ、しかし、それを「フィクション」として疑ってかかる必要はないのか、小説の筋書きは裁判記録と完全に一致しているので、つまり裁判記録自体を疑ってかかる必要はないのかと − 常識は要求していたと、僕は思う。
川村湊のこの本は、その点を確認してくれた。つまり、あれから 30年、当時の清張の作品の「何が問題なのか」を、ようやく説明してくれたようだった。
詩人としての林和と、それに深い影響関係にある中野重治の「雨の降る品川駅」との関係も、この評論で整理されていた。つまり、この作品の検閲による削除部分を、中野自身は復元をしぶっていた事情、その朝鮮語訳 全文を水野直樹が発見して原文復元し、中野に承認を迫ったこと、これに対応する林和の「雨傘さす横浜の埠頭」 − そういう関係を整理するものとして、この本のこの章は貴重だと僕は思った。
981129-2: 川村湊:『満州崩壊−「大東亜文学」と作家たち』/小林勝外伝
林和や中野重治と比べると、小林勝の知名度はぐんと落ちる。が、この作家は、70年代には「日本人と朝鮮の関わりを問題視する作家」として、まだ有名だった。
この作家の作品を、僕は全文を通して読んだことがない。理由はただ1つで − 読むこと自体が非常にゆううつだったからだ。
いま整理してみれば、こうなる: この作家の世界は、今となって使える言葉で言えば「朝鮮に対する贖罪意識に満ちていて」、読者にもその前提を強いる。その前提が成り立たない限り、この作家の「作品」は、読者として とても読めたものではなかったからだ。
川村のこの本のこの章は、文学/詩人青年だった川村自身の投稿に小林勝のぼろくその評を受けた場面からはじまる。「評論」としては異色で、書き手自身の独白である。
感情面で相当なトリガーを含むこういう話題は、普通の「評論」文体では書きにくい。20年以上を経過した後に、彼はそういう表現方法をもって、ようやく小林勝を正面から批判する回路を手に入れたのだろうか。
結論的には、川村は小林勝の作品群に、大きく否定的である; 特に、植民地に生まれそれ故に「朝鮮」に強いこだわりがあることと、このこだわりが あくまで 朝鮮人と日本人の運命共同体幻想の上に成り立っていたことを指摘する。つまり、朝鮮という植民地に生まれた小林の大前提には、宗主国である日本の国民である無意識の優越感と、その裏返しである朝鮮への憐憫があることを、川村は露骨ではないが遠回しな言い方で指摘する。
僕自身は、この川村エッセイで小林勝への最終的な解答を得たような気がしている。
(このファイル終り)