ハングル工房 綾瀬 - 僕の朝鮮文学ノート 9810
Hangeul-Lab Ayase, Tokyo
ハングル工房 綾瀬店 ホームへ
文学ノート全体目次へ
Mail to home master: Ken Mizuno
981026-1: 朝鮮文学なんてマイナーな分野
困りましたねえ ...
だいたい、読者がいないんです。昔から、朝鮮関係の本なんて売れないと決まっていて、出版社からは きらわれる分野の最たるものです。1960年ころ、金素雲さんだってそれで苦労した。1970年ころ、今では伝説の同人誌『朝鮮文学』を出した長・田中・大村の三羽ガラスだって、これが商業ベースで成立しないと踏んだからこそ、「同人誌」という形態を選んだのでした。70年代となると、大阪には国立外大に朝鮮語学科が存在しています。その大阪の外大にも、朝鮮文学趣味は存在したから、学生の同人誌は存在しました。でも、それは「東京」の圧倒的な情報伝播力には無力だったし、何よりも「三羽ガラス」3氏のそれがプロの意識に支えられていたのに対して、大阪の学生同人誌はあくまで「学生の」それにすぎなかったことが、大きな限界ではありました。
僕がその「大阪」の学生になったのは、1973年の春でした。
前年には、あの感動的な「7.4南北共同声明」がありました。
それからおおよそ 10年、僕は朝鮮語屋でした。初期には歴史屋を志し、次は言語屋を志し、最後には主任教授から「水野くん、きみ、朝鮮語ができるんだってな」と言われたころには、僕は朝鮮近代文学をテーマとして、たった一人で「世界中の朝鮮屋の中で、近代文学を語れる人物になろう」と考えていたのかもしれません。
ただ、僕は「文学」趣味には無縁です。美文・麗文を駆使して美辞麗句を並べる技術が「文学」だとは、とうてい思えないし、まして そういう文面を僕自身が書くことはできないし、その能力もない。「文学とは何か」という高踏的な問いに対して、僕は今でも明快な解答ができないままです。ただ、「文学」とは少なくとも独善的な・自己陶酔による作文を意味するのでもないし、天下国家の正義を「文字によって」表現したものでもないと思っています。
「文学」とは、媒体として「文字」を使用し、その媒体つまりメディアを通して「何か」を訴えるものです。それを、専門用語では「自己表現」またはその回路と呼びます。すべての文字(言語)行為は自己表現の一種であり、そして、そうやって表現されたものの「ある」ものが「文学」と呼ばれる傾向にある;つまり、歴史の中に存在する、文字として残されたものの「ある」ものだけが、歴史に中で「文学」と呼ばれる資格を獲得するんですが、
さて、それでは「何が」文学なんだか、さっぱりわかりませんわ、なあ。
とりあえず ここから先の「文学」論は、歴史の中で「文学作品」として認められたものを扱う − なんて言ったって、やはり具合が悪いですね。ここは無難に、「世の中に一応名の通った」作品を想定する、そういうことにしましょうか。本当は それでは具合が悪いですが、まあ、とりあえず。
981026-2: 金芝河
あまりにも有名で、それも「現在」の作家なので扱いにくいせいもあるが、それを別にしても、これほど評価の別れる作家(詩人)も多くない。kim-ji-ha。
60年代後半、金芝河の登場は鮮烈だった。
日本は、まだ「北は天国、南は地獄」の時代だった。1965年の日韓条約反対運動、その背後に「南は地獄」論、そして、運動側はすぐれた詩人を発見した − 民族詩人、叙情詩人、民主主義の闘う詩人、獄中の詩人。
彼の初期の作品、例えば『黄土 hwang-tho』は、叙情詩だった; それも、少女の感傷を綴った2流の叙情詩ではなく、例えて言えば「南朝鮮民衆の苦しみを」文字通り「詩的に」表現したものだった。20才のころはじめて日本語訳で読んだ僕は、その鮮烈さを今でも忘れない。その後に見た原文は、むずかしかった。方言が使われていることもあるが、「詩」に使われる言葉の1つ1つが、「詩の言語とはこういうものだ」と思わせるような密度を持っていた。散文は論理の表現、詩は言葉の密な連鎖を最低限の語数で表現するのだと思うようになったのは、僕には、当時の金芝河の影響が強い。ただ、『五賊 o-jeok』の地口はいただけなかった。言葉の遊戯それ自体のおもしろさ、それはよいのだが、しかし今になってみると、金芝河は『黄土』の叙情性を『五賊』で既に失っていたのではないかと、僕は考えるようになった。乱暴な言い方をすれば、『五賊』は地口と語呂合わせによる政治詩?にすぎない。言葉はおもしろいが(読むのは大変ですよ、念のため)、『黄土』で表現しようとした「何か」と、『五賊』のそれとは、本質的に異なっている。
72年の南北共同声明、それを追う 朴正熙 pak jeong-heuiの「維新体制」、74年には民青学連事件。そして『民衆の声 min-jung-eui so-ri』。
『民衆の声』の訳文が出回ったとき、僕は疑問を感じていた − これが、あの『黄土』の作者の作品だろうか? 誰も相手にしてくれなかったが、この文面には『黄土』の「暗さ」がなかった。「暗さ」とは、他のどんな回路でもない「言葉によって」自己表現をはかること、それが叙情詩であるだけに ほとんど必然的についてまわる、ある・ひそかな精神の戦いのようなもの、のことだった。『黄土』にはその「暗さ」があり、それが「文学」の一部をなしていた。しかし、『民衆の声』にはそれがない。これは、何のことはない、彼が闘っている韓国政府側の、街にあふれている「北のスパイ、見つけたら申告しよう」とか「明るいセマウル、こぞって参加」とかいうスローガンと同じ(言ってる内容がちがうだけの)標語が並んでいるだけだ。こんなの、「詩人」の作品ではない。
(金芝河は出獄後、新聞社のインタビューに答えて、最終的にそれが「自分の作品」だと認めた。集団創作の末に、金芝河が最終稿にした、と受け取れた)
1980年ころ、金芝河は「大説」を書いている。「大説」とは、矮小な名前をもつ「小説」とは反対の概念だそうで − うーむ、なるほど、少なくとも近代文学の一部である近代小説の概念からは、だいぶ遠いものでしたね。題は忘れた。今でも書き継いでいるのだろうか?
詳しい方はご存知だが、朝鮮開化期の独立運動家に 申采浩 sin chae-ho 1880-1936 という人がいる。最近の朝鮮近代文学の全集には、この人の「小説」、表題『竜と竜の大激戦 yong-gwa yong-eui tae-gyeok-jeon 』というのが載っている。政治家の書いたものなので、あまり期待はできない − いや、その、講談まわしのフィクションというか童話というか、とてもじゃないけど「文学」として鑑賞するようなもんではないのだが、金芝河の「大説」って、これとそっくりなんですね。
補足:もし申采浩の作品に興味のある方は、そうですね、安国善 an-guk-seon の『禽獣会議録』をご存知だろうか。『竜と竜の大激戦』は この『禽獣会議録』の時代の作品で、申采浩もまた「文章による開化啓蒙」ということを実践した証拠ではある。内容はもちろん、正と邪の二匹の竜が戦う − もうおわかりですな。
僕の私的な朝鮮文学 − 詩、散文、言葉の論理
このノートは、そもそも僕の私的な体験と思いを綴ろうと思って設定したのだった。
何をまちがったか、つい突発的に金芝河を思い出して上に書いたが、別に僕は金芝河を朝鮮文学を読む出発点にしたとは思っていない。何よりも「詩」は、高校生だったころの僕にさえ遠い存在だったし、自分が「詩を理解する」人間だとは思っていなかったから、「詩」または「詩人」はあくまでよその世界の、言葉の「また もうひとつの世界」にすぎなかった。だから僕は、金芝河の『黄土』ではじめて「最小限の言葉で高い密度の」世界があることに驚いた;裏返せば、その後の展開への失望も大きかった。いずれにしても、「詩」の言葉の論理展開と「詩」本来のイメージの継起連鎖の関係は、僕には長い間「鬼門」だった。だから、解放後「北」に移った何人かの詩人の作品にしても、僕は それが「詩」であるがゆえに、半ば「避けてきた」と言っていい。
それよりも、僕は散文 一辺倒だった。「文学」趣味の自己陶酔を誘いやすい「詩」にくらべて、散文は論理の戦いであるという観念は、今でも僕にはある。「論理の戦い」という言い方を誤解しないでほしい; 近代文学でいえば、例えばドイツの『若いベルターの悩み(若きウェルテル?の悩み)』、日本では森鴎外の『舞姫』。高校生のころ読んだそんな散文作品に、僕は「言葉によって」何かを表現しようとする作者の、内面の「ある」必然性を感じていたと思う。つまり「言葉という回路を通して」作者は自分の中に渦巻く ある「観念」を表現しようとしていた。その表現は、しかし あくまで「言葉」によって「説明」されるばかりであって、決して その言葉のイメージに依存することがない。それが「散文」作品なのだと、僕は考えていた。
観念を表現するだけなら、官僚作文だって、歴史の論文だってそうかもしれない。しかし、政治家の空虚な言葉、無味乾燥な歴史論文の言葉に対して、ある種の小説たちの言葉は生きていた。このちがいを説明することができるのか。
表面的には、小説はフィクションだった。では、フィクションならすべての創作は人を感動させるのか。
文学の教科書には、「説明」と「描写」の区別が書いてある; 絵の教師たちも、「絵は説明ではない」という(だから「絵」は見た印象を描け、図面を書いているのではないのだという)。どんなに「説明」をつくしたマニュアルも、人を感動させることはない; かえって、くだらないワープロ・ソフトのマニュアルは分厚いばかりで、誰も読んではくれない。
「ベルター」にも「舞姫」にも、「説明」はあるが言葉のイメージへの依存はない、と上で書いた。文学の教科書は、それを「描写」であって「説明」ではないという。僕が言う「論理の戦い」とは、図面を書くのではない「絵」を描く意味で、作者が自分の世界を描写し、そのことによって「自分自身を表現する」ことに力点がある; そのとき、言葉が生きている; それは「詩」に比べればはるかに「説明」にすぎないのだけれど、しかし政治家の空虚な言葉に比べると はるかに生きた言葉の世界があり、それが僕の言う「散文」だったような気がする。その散文の世界は、「詩」の言葉のイメージ喚起に頼るわけにはいかないから、あくまで「論理」を組み立てようとする。ストーカーに近い愛の告白を続けるベルターには、その告白を論理的に説明する必要があった。女を妊娠させて裏切り発狂させた鴎外には、それに至る自分の内面を論理として読者に納得させる必要がある。「散文」作品は、いつでも「論理の戦い」をくりかえしている。
具体的に「ベルター」と「舞姫」の2つの作品は、「論理」をつめれば「自己正当化」をしているにすぎない。それにもかかわらず これらの作品が「近代文学」である理由は、おそらくただ1つ − 前近代の類型化と勧善懲悪のパターンを脱して、「近代的自我」を正面から扱った点だった。少なくとも僕は、「近代文学」の重要な要素として、「個」の認識とその表現を必須事項だと考える。だから、「近代」初期の作品には、日本でも西洋でも、露骨な・露悪的な・自己中心的な・不健康な・性的衝動が描かれてきた。「近代文学」をそれゆえに非難することはたやすい。しかしそれを非難するあまりに、「文学」が天下国家のステレオ・タイプの正義と勧善懲悪に回帰するなら、それは「近代」文学ではない。つまり僕は、金芝河の「大説」を近代文学ではないと考えている。近代文学がその「不健康さ」を克服したいなら、「ベルター」と「舞姫」の自己正当化を批判すると同時に、それを越える「何か」を模索するべきであって、前世紀の勧善懲悪民族的正義のステレオタイプに堕すべきでは、ない。「個」の認識のないセックス一般を扱うポルノは、どれほど露骨な性交描写があっても「近代文学」ではないし、「個」の認識のない「作品」は、たとえ Webのホーム・ページに掲載された作品であっても「近代作品」ではない。たとえば『禽獣会議録』は、「外面的(表面的)な近代性」を帯びた作品ではあったが、その意味で、つまり内実において少しも「近代的」ではなかった。ただ、天下国家中華礼儀の国の禽獣が、「堕落」し「親日化」した人類を叱咤するばかりの作品だった。
一時僕は、植民地下の朝鮮を逃れ独立運動を展開する大韓臨時政府 参加者の「手記」に凝ったことがある。それ自体は、感動的な手記だった。と同時に、それは 朴正熙時代の反体制運動と連動していた。この臨時政府に関わった当事者は、70年代の韓国には何人か発見できた。そしてその当事者間に、実は深刻な感情的対立があることを知った。多少、冷めた。
「散文」の世界は「論理の戦い」の世界のはずだった。しかし、臨時政府当時の参加者たちの対立は、対立が単に感情の対立であって、論理の戦いになっていなかった。ノン・フィクション「文学」である可能性をもったこの手記たちの魅力は、薄らいだ。そこには、ゲーテや鴎外の自己正当化さえ希薄だった。手記が、ノン・フィクションであるより過去のアリバイ作りの道具になるとき、作品は(「文学」の観点からは)堕落しはじめる。
(しかし、なつかしい; 僕はその手記を夜を通して読み続けていた。これはいずれ項目を立てて語ってみたい話題ではある。植民地期の「独立」運動は、満州のパルチザンとアメリカのロビーばかりではない)
そして、そういう現実の生臭さと無縁のところにあるのが、『サラン(バン)のお客様とお母さん sa-rang(bang) son-nim-gwa eo-meo-ni』みたいな世界だった。
(突然「サランバン」で、笑わないでね; どんなに少女趣味だと笑われても、この作品を近代文学史から排除することはできない; 現代の文学史家が何を言おうと、天下国家社会の正義をふりまわしたがるこの国の文学史の中で、この作品は、逆にきわめて重要な意味を持っていると、僕は今では考えている)
981028-1:『サラン(バン)のお客様とお母さん』
表題は sa-rang(bang) son-nim-gwa eo-meo-ni、あるいは bang の付くのが正解だが、韓国の活字本にはこれが脱落したものがある(多い)。原作初出を見ていないので正確なところはわからないが、「おそらく」半ば意図的な、半ば無意識の改変で、この1文字が脱落するとたいへん示唆に富んだ表題になるからだ。
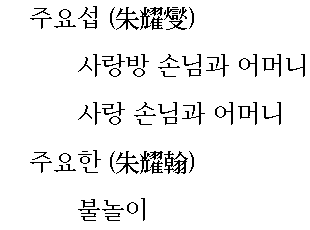 作家は ju-yo-seop、この漢字が JISにないようなので、作品名とともに「絵」で示す。
作家は ju-yo-seop、この漢字が JISにないようなので、作品名とともに「絵」で示す。
この作家の兄は ju-yo-han、有名な詩人で作品に『pul-nor-i』などがある。ご参考までに、兄の名前は「ヨハネ」、弟は「ヨセフ」と読める点は、気がついてもいい。この点、作品「サランの ..」にも、カトリックと思われる「教会」や「主祷文(マタイ 6-9、ただし最近は「主の祈り」とも呼び、カトリックではマテオとも言う)」が出てくる。
「サランの ..」の作品年代は、現代の年表では 1932年。場所は、おそらくピョンヤン近郊。作家自身がピョンヤンで生まれている。この時代、この都市はカトリック教会を含む近代化の中心地だった。
なお、解放後の韓国ではこの作品が複数回 映画になっているが、内容にも時代設定にも大きな改変があるので、映画をご存じの方は、それを記憶にとどめてほしい。原作はあくまで解放前の、朝鮮語抹殺政策が展開される前、1919年の3.1運動から 10年少し後の作品である。
私は(数え年)6才の少女である。父はいない。私が生まれたころ死んだそうだ。父はこの地に教師として赴任し、そこで結婚したので、私たちは今も母方の実家近くに住んでいる。父が死んでから、生活は苦しい。父が起居したサランバンがあいているので、下宿人がやってきた。死んだ父の友人で、やはり学校の教師に赴任してきた人だ。私は、このおじさんと友達になる。そして私は、小さな愛のメッセンジャーとなる ...
僕のあこがれた近代文学研究者、長璋吉氏は言ったものだ:「純真無垢を絵に描いたようなこういう語り口は、(俺は)だっきらいなんだ」。
うーん、そうですねえ、先生、しかし、この作品を除いて、近代朝鮮文学で、高校生に読ませられるような作品なんて ないでしょう、先生。
僕は、この作品の訳を、学生出版物に載せていた。驚いたことに、それをコピーして、生徒に読ませた高校の現代国語の先生がいた。僕は何通かの読書感想文を受け取った。そのどれもが、ちょうど『若いベルター(ウェルテル?)』や『舞姫』の感想文とそっくりな、素朴で生意気な少女の感動を伝えてくれるものだった。この作品は「いける」; 僕はそう思った。暗いばかりの朝鮮近代文学の中で、これほど天真爛漫を装った少女の語り口で、前世紀の遺物のような訓戒と勧善懲悪を口にすることなく、それへの「戦い」を声高に振り回すのでもない、ただ叙情的に、若い寡婦と、亡き夫の友人である後任教師との淡い愛情を描いた作品 − こんな作品は、めったにみつからない。
「叙情」的であろうとして美文麗文に陥る「純粋文学」作品ならいくらでもある。「民族」の歴史を講談まわしで語る作品、民衆の戦いを声高に語る作品も、完成度を問題にしなければ、山ほどある。が、小説、つまりフィクションがフィクションとして完結し、その中では少女の語り口を使うことによって余計な「主義主張」の入り込むすきを排除した、こういう作品はめずらしい。
もちろん、「少女の語り口」、天真爛漫を装うことそれ自体が「鼻につく」、そういう面はある。しかしそれは、「この」語り口をとる以上 宿命的であり、逆に少女の語り口をとらなかったら、この作品もまた(同じ作家の同時期の作品群のように)悲惨な現実とその中で身悶えする悲しい女の姿・という、ある種の、安易なステレオ・タイプに陥るしかなかったのではないか。この作品の成功は、どこまでも「少女」に語らせる技巧にあったと言っていい。裏返すと、作家には失礼だが、この作家の他の作品にはほとんど見るべきものがなく、ただ「サランの ..」だけが技術的(技巧的)に成功している。
ただ、「技巧」は、登場人物に対する作者の近しさにも関係するだろう。ステレオ・タイプによる「悲惨な女性」像は、この作家では(例えば)大学教授の1人称、つまり観察文体で書かれている。この場合、話者が観察者である分だけ、作品は少しも「文学」や描写にならず、ある種の正義感によって文章に記録する、という形になる。記述はあくまで、通りすがりの傍観者の立場に終始する。
「サランの..」は、その点が異なる。子供の語り口では、作者は自分の抱懐を述べる余地はない。あくまで、子供の認識という間接的な表現を取らざるを得ない; そのことによって、観察は「女・子供」の認識世界に踏み込む。作家は天下国家の正義を論説するよりも、彼(女)らの世界への想像が忙しくなる。結果として「文学」は文学らしく、母と子の日常の微細な交渉の中に、読者は「フィクション」であると知りつつ そこに「生きた」世界があることを読み取れる; この回路は、傍観者の視点で書かれた作品には存在しないものだった。
フィクションでありながら生きた世界を想像させる作家の力を、作家の「想像力」という。その想像力は、同じ作家がステレオ・タイプの記述でどれほど「想像力」をたくましくしても作り出せない、「生きた」作品を生み出すことがある。この本来の想像力は、実は小説技術を飛び越えて「ど素人」の大作を生むことがあり、例えば少女が1夜?の間に「風と共に去りぬ」を書き下ろしたりすることもあるが、これは別の話題で、
いずれにしても、「サランの ..」は技巧面で安定した分だけ、人物の描写が生きている。逆に主義主張とステレオ・タイプに陥るとき、作品は読み終わった瞬間に忘れられてしまう。この作家の作品について言えば、事実上 生涯ただ1つ、この作品しか成功したものはない。
近代朝鮮文学は、悲しいことに「日本」を悪としそれに戦いをいどむ勧善懲悪ではじまった。その限りでは、(「戦い」のあり方に「近代性」を発見するのでない限り)朝鮮近代文学は前世紀の遺物を近代活字と近代語に置き換えただけだった。が、1932年のこの作品は、近代的な「完結したフィクションとしての短編小説」として、僕がはじめて出会ったものだったし、それ以前にも以後にも、少なくとも植民地期の小説にこれだけの完成度を示すものは、多くない。
(この項 未完。長くなりそうですね)
981031-1: 『サランの ...』の円環構造
「サランの...」には、注目するべき、かつ古典的な「円環構造」が見られる。
つまり、小説の導入部で提示された「現在の」環境が、「ある」事件によって何がしか「揺さぶられ」、その事件によってある展開が見られるが、小説の末尾では「事件」はすべて解決されて、結末は「小説開始前の状況に回帰する」構造を言う。
この「構造」は、古いところでは中華古典の『桃源郷』にある。ある農夫が道に迷って桃源郷に踏み込む; そこには理想郷が展開される(なつかしいですね、高校の漢文教科書 − 昼の犬がなき、ニワトリが鳴く世界); 農夫は、一時そこを去り、後に再び桃源郷を求めてさまようが、ついに再び・その入り口に到達することはない。
つまり、「桃源郷」は閉じた世界であって、その発見・離別という入り口と出口は閉じていて、離別とともにその過去は失われる; 後にその世界を探しても、それは再び発見されることはない。
サランのお客さまは、ある日 突然やってくる。そのお客様をめぐる少女オッキ ok-heuiの世界と、それを媒介とする二人の淡い愛情は、小説の結末とともに閉じられる; お母さんが再びその愛を取り戻すことはないと、小説の末尾は 事実上それを示唆している ...
この点をあげて、「サランの...」の「非・近代性」を指摘した韓国の評論を読んだことがある。
僕に言わせてもらおう: もしそれで「サランの...」の近代性が否定されるなら、「舞姫」が第1に「和紙に毛筆で書かれたこと」、第2に「女を妊娠させそれを裏切り発狂させたこと」によって「舞姫」は近代作品ではないと主張するに等しいか、それに近い立論だと思う。
「舞姫」は、ドイツに留学しそこで勉学につとめ その一方で現地の少女に出会い 同棲し 妊娠させ、結婚を裏切り帰国して少女を発狂させ、そして少女の消息はその「死」を示唆することによって「円環」構造を閉じる作品だった。それは、残酷で自己中心的な作品だった。しかし − しかし、「話」の内容が残忍であることと、小説の技術的なあり方とは別なのだ。この作品は、ドイツ留学という青春のある時期を支配する、ある時期における青年の内面を表現している; その内面の「ある」暗い部分は、妊娠させた少女を切り捨てるという否定的な面を露骨に表現しているからこそ、その部分で「こんなもの、どこが近代文学なのだ」という反発を誘うと同時に、そうした「個の内面」を露骨に表現したからこそ「近代」文学なのだという論理が成り立つ。そして、少なくとも日本近代文学に関する限り、「舞姫」はその意味で、つまり後者の意味において、現在も「近代」作品であるはずだ。
「サランの ..」の円環構造 − つまり、サランバンにお客様がやって来、そのおじさんとオッキが友情を結び、オッキをメッセンジャーとする二人の愛の交渉、そして それを拒否するお母さんと、結果としておじさんは去って行く、そのことによって母子は再びもとの日常に回帰して行く − は、ある意味で 193x年という社会の中での、「ある」社会の「ある」断面を表現していることは、まちがいがない。僕は、その意味でこの作品を「歴史のある断面を表現する」作品として、その状況をビビド vividに伝えるものとして、賞賛を惜しまない; つまりこの作品は、「舞姫」のある「否定的な」面より はるかに肯定的な面を示すものとして、僕は「近代」作品であると考えている
981101-1: 『サランの ...』の円環構造とその映画
しかし、そういう勇ましい近代文学批判(例えば『舞姫』のどこが近代的なんだという、あんなもの、女を何と思っているのだという批判)は、日本でも現に僕が聞いたことのある批判では ある。前近代の『春香伝』やそれに類する(変な言い方だが)「古代小説」の勧善懲悪パターンを脱するものとして、「サランの..」や「舞姫」の世界にショックを受けていた、「文学」にナイーブな(無知な)青年だった僕は、この「批判」にたじたじとしたものだ。しかし、それでも「舞姫」が近代作品であることは変わらない。この作品をどんなに非難しても、青年期のドイツ留学、その中で出会った少女との交渉を、ここまで・青年の内部に即して説明(描写)したものは、前世紀にはない; その意味で、これを近代小説と呼ばなければ、何を「近代」作品と呼んだらいいのだろうか。「舞姫」が和紙に毛筆で書かれていてもかまわない。擬古文であることが「近代」性の否定にはつながらない。「サランの..」の原文がどんなに古色蒼然とした朝鮮語であってもかまわない。問題は、それが近代的な自我を表現しその内面の戦いを表現しているかどうかだ。
ただ、この「近代」批判は、日本より朝鮮文学において はなはだしい傾向はある。
朝鮮文学は、昔から「作品が作品として(フィクションがフィクションとして)自立せず、作品が現実と直結している」傾向があった。つまり、作品の中から「現実」に向けて、現実的な主義主張が発信されなければ、それが天下国家社会の正義を代表する「文学」として、社会的に認められない傾向が、あった。
「サランの...」には、この「天下国家の正義の主張」が欠けている。少女の語り口を借りてしゃべるのに、どんな天下国家の正義があるのかは知らないが、しかし作品は円環構造をとっていて、天下国家儒教的正義に対する抗議は、作品中には希薄にしか表現されていない。だから、韓国の「参与文学」評論家は、この円環構造、抗議することもなく運命に従う「お母さん」の姿を、敗北主義だと言う ...
だから、解放後の韓国の映画は、この点を大きく改変または追加する。
サランにやってきたおじさんは、お母さんと淡い愛情の可能性を示す; メッセンジャーとして少女は、その愛の手紙さえ運ぶことになる; しかし、原作には、愛情当事者の「どのような直接対話もない」。映画を見た方は驚くかもしれないが、原作では、二人は最後まで直接の接触どころか、会話もしない。ただ、少女を介して、間接的に相手を想像するだけなのだ。
そして、愛の手紙の拒絶によって、サランのおじさんは去って行かなければならない。作品の設定は、一貫している。
解放後の映画では、その点を大きく改変する; 最初の作品は見ていないが、聞くところによると「女の再嫁」を否定する儒教道徳への抗議が示されるという。原作では、それはわずかに、「おじさんがアッパになったらいいなあ」という子供のせりふと、例のごとく夜 泣く母親のせりふに集約されるあたりか。
2作めと3作めの映画は同じ製作者によるもので、2作めは廃棄されているかもしれない;3作めを僕は見た。
儒教道徳の伝統への抗議は、母親の母親(話者少女のおばあちゃん)の説教に示されていた。それ自体は、どうということもない。
この映画の巨大な改作は、母親の兄が出てきて、「これからの時代、お前も再嫁を考えよ」と、強く説得することにある。
2作めと3作めには大きな変更があるそうで、廃棄されたと思われる2作めでは、映画の末尾で「おじさん」の「妻」が、その本家の危急を知らせに来る。つまり「おじさん」は既婚であったのだが、3作めでは危急を知らせる女は「おじさん」の妹になる。
つまり、3作めでこの映画は態度を決定して、おじさんが去って行く理由を「別に」作り出し、かつ危急を知らせる女が妹であることによって、おじさんの社会的道義的潔白を示す。作品の力点は、伝統的儒教道徳による社会的束縛への抗議に移動し、愛情の相手であるおじさんのアリバイも完璧(独身)になる。
解放後の韓国でも、天下国家社会の正義を表現すべし・という「文学」に対する要求は強かった。ある意味では、それは現在も続いている。そういう環境の中でこの作品が映画化されるとき、映画は、「大衆の」要求を受け入れる; つまり「サランバンのお客さま ...」は、あくまで伝統的儒教道徳への抗議を体現する作品でなければならなかった。だから、映画は改変される。
原作は、死んだお父さんの友人が下宿人としてあらわれ、その人とおかあさんの「淡い」愛情の可能性を示す、そしてその実現の愛の手紙をお母さんが拒否することによって、おじさんはそこを去って行く、だけである。
それで、何がいけなかったのだろう?
原作が暗示する「儒教的束縛」とその文化はわかる。しかしそれを明示し声高に語ることによってしか、韓国の社会派評論家はこの作品を評価できないのだろうか? 映画は、それを先取りするかのように、時代設定さえ変更して(解放後の韓国の南の地方になっている)、束縛からの解放を訴える作品になっていた。
それにもかかわらず、この作品つまり小説原作は、韓国の少女たちの愛読書になってきた。これだけ深刻な「活字離れ」現象の中で、文庫全集の中のこの本は、いつでも手に入る。1974年だったか僕が初めてこの作品を読んでから、199x年にも手に入る。
おそらく、「舞姫」や「ベルター」が日本の少女たちの愛読書であるのと同様に、「サランの...」は韓国の少女たちの愛読書になっている。そして、少女たちは、何を感じているのだろうか。
ま、もっとも、活字離れ現象の中で、少女たちだって「サランの...」は映画の記憶でしか知らないかもしれませんけどね。
(このファイル終り)
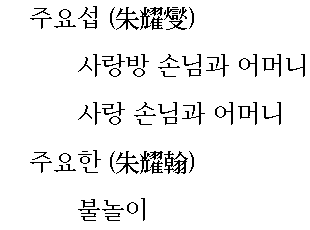 作家は ju-yo-seop、この漢字が JISにないようなので、作品名とともに「絵」で示す。
作家は ju-yo-seop、この漢字が JISにないようなので、作品名とともに「絵」で示す。